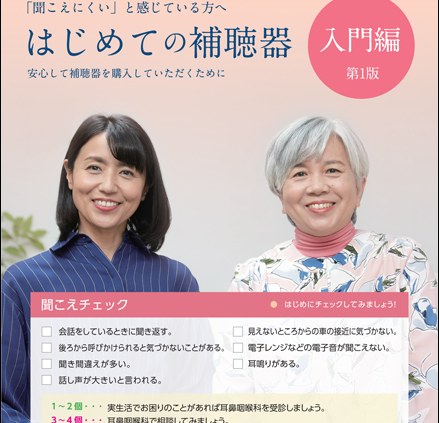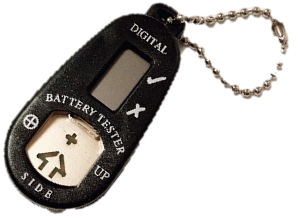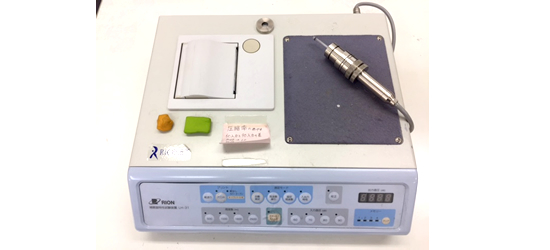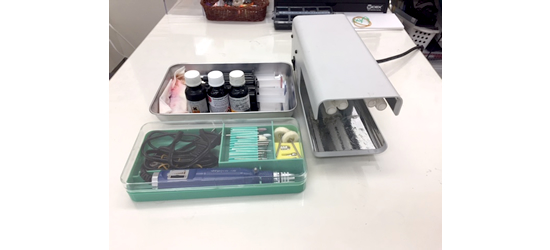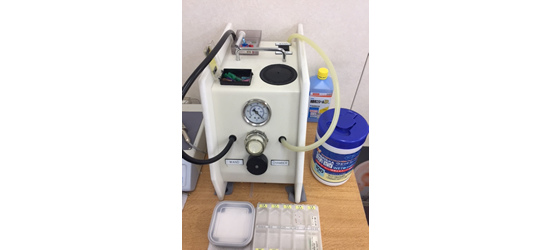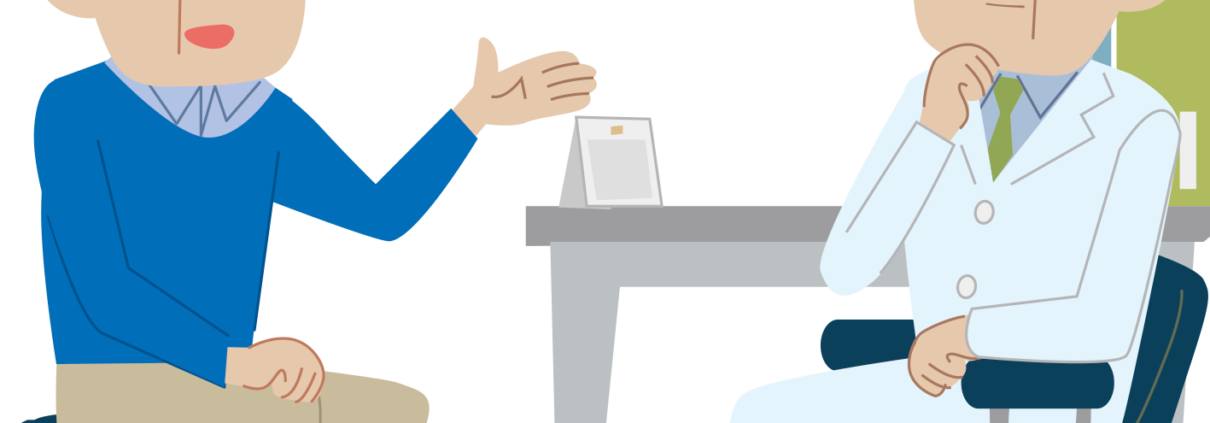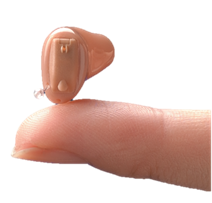9月半ばを過ぎても猛暑日と異常気象が続いております。
暑い日は冷房など使って、涼しい所で休みましょう。
補聴器専用の電池があることをご存知ですか?
見た目はボタン電池に似ていますが、補聴器専用電池は他の電池と構造が違います。

補聴器の電池は、「空気電池」といい、周りの空気を取り込み、化学反応によって電気を作っています。
空気によって電気を作るため、他の電池と取り扱いが異なります。
今日は空気電池の特徴について話します。
空気電池の使い方
(空気電池のシール)
空気電池には、必ずシールが貼ってあります。
どうして、シールが貼ってあるのでしょうか。
実は、シールが空気電池の空気孔を塞ぎ、電池内部に空気が入らないようにしています。
空気電池は、空気が入ると化学反応を起こし、すぐに発電を始めます。-
そのため、真空状態を保つため、シールが貼られています。
(使い方)
はじめにシールをはがしてください。
そして、ここで注意するのは、電池をすぐ補聴器に入れないでください。
はがした直後は電圧が安定していないので、補聴器の動作が不安定になる場合があります。
シールをはがして1分ほど、手で軽く握るのが最適です。
1分ほど経ったら安心してお使いいただけます。

空気電池の寿命
空気電池の大きさによって、電池寿命は異なります。
補聴器で使用する空気電池は4種類あります。小さい順に紹介します。
※電池寿命は1日10時間ほど使用した場合の日数
PR536(10A) 黄色 電池寿命:5日~1週間ほど
PR41(312) 茶色 電池寿命:1週間~10日ほど
PR48(13) オレンジ色 電池寿命:2週間~3週間ほど
PR44(675) 青色 電池寿命:1カ月ほど
空気電池は覚えやすくするため、シールに色がついています。
この色は世界共通なので、海外で電池を購入する場合も色を覚えれば購入する事ができます。
(電池寿命のちがい)
1つの電池で寿命に差があるのには、理由があります。
空気電池は周りの環境によって、寿命が変わります!
空気を取り込んでいるので、その取り込む空気によって変わるのです。
では、空気電池の寿命が短くなりやすいポイントを紹介します
・寒さ
・乾燥
・二酸化炭素
この3つが短くなる要因といわれています。
なので、空気電池は「冬」に寿命が短くなりやすいです。
1年を通して補聴器を使うと、電池交換時期に違いが出ます。
しかし、故障ではありません。空気電池の弱点が関係しています。
空気電池の保管
では、どのように使うと寿命が長くなるのでしょうか。
常温・常湿が最適です。
冷蔵庫や乾燥ケースでの保管はあまり向いていないです。
また、直射日光や高温・多湿も避けてください。
補聴器を入れる乾燥ケースには、フタ部分に空気電池が置ける場所があります。
そこに空気孔を下にして置くと、少し寿命が長くなるらしいですよ。
ちょっとしたやり方で寿命が変わるので、お持ちの方はやってみてください。
寒い冬は、朝使う時に空気電池を手で暖めてから入れるといいですよ。
シールをはがした時と同様、1分ほど手で軽く握って暖めてください。

質問①
(使っている空気電池の残量を知りたい!)
環境によって左右される空気電池だからこそ、残量を知りたいと思います。
お店では、電池の残量が簡単に分かる「電池チェッカー」を販売しております。
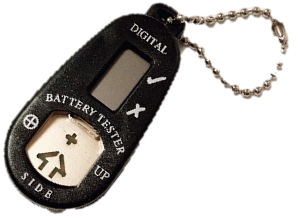
使い方は簡単!電池を金具部分に押し当てると、上部にあるメーターが残量を教えてくれます。
電池チェッカーには、電池収納があり、予備の電池や使い終わった電池をしまう事ができます。
質問②
(補聴器を使っていないのに電池が切れた)
空気電池は、化学反応によって発電しています。
そのため、使っていない時でも微かながら発電し、残量が減っていきます。
ただ、補聴器使用時より減るスピードは遅いです。(消耗量が少ない)
久々に補聴器を使おうとしたら、電源がつかず、調べたら電池切れが原因だった方もいます。
質問③
(充電式補聴器には空気電池は使われていますか?)
使われていません!
充電式補聴器にはリチウムイオン充電が採用されています。
スマートフォンやパソコンでも採用されている電池です。
最後に…
補聴器の電池は「空気電池」という特殊な電池を使用しています。
空気電池で気を付けてほしいこと👆
・シールをはがして1分ほど手で軽く握って暖めてください
・冬は電池の寿命が短いですよ
電池交換したくないという方には、充電式もあるのでご安心ください。
タスク補聴器では、空気電池式・充電式どちらもお試しいただけます。
補聴器は長く使うものなので、快適に使える方をお選びください。
補聴器のご相談をいつでも承っております。
スムーズにご案内できるご来店予約は、お店へのお電話とホームページからできます。
ホームページからご予約される方は、こちらをクリックしてください
皆さまのご来店を心よりお待ちしております
認定補聴器専門店 タスク補聴器